岸和田だんじり祭り2024日程|だんじりの意味・神輿との違いは?
岸和田だんじり祭り2024日程
秋になると全国各地でお祭りが開催されます。
皆さんはどんなお祭りを思い浮かべるでしょうか?
行ってみたい日本の秋祭りランキングで、いつもトップに来るのが「岸和田のだんじり祭り」


では、2024年の日程はどうなっているのでしょうか。
岸和田だんじり祭は、毎年敬老の日の直前の土、日に開催されます。
ということは、2024年の開催日程は…9月の14日と15日になります。
1日目の9月14日は「宵宮」で、朝6時の市役所からのサイレンを合図に、各町のだんじりが一斉にスタートします。祭りの終了は午後10時です。
2日目の15日は「本宮」で午前9時から始まり、やはり午後10時まで開催されます。
さて、だんじり祭といえば、余りにも「岸和田」が有名なので、だんじり祭りは岸和田だけと思っておられる方も多いでしょう。
いえいえ、だんじり祭りは岸和田だけではないんです。
恥ずかしながら、かく言う私も、実は昨年初めて知りました。まあ、それくらい、だんじりと言えば岸和田、というイメージが定着しているのでしょうが。
そんなわけで、今回は比較的知名度の高い、他の地域のだんじり祭りの日程について調べてみました。

これを機会に、お近くの方や、「色んなだんじりを見たい」と思っている方は、一度観に行かれてはいかがでしょうか。
また、だんじりの意味や由来、岸和田だんじり祭りの見どころについてもご紹介しています。
だんじりの雑学を手に入れて、お友達などに披露するのもいいかもしれませんよ!
各地のだんじり祭の日程と場所
※現在の日程は予想が含まれています。
日程が詳しい情報は再度確認をお願いします。
誉田だんじり祭り:大阪府羽曳野市誉田八幡宮
日程:2024年9月14日(土)~9月15日(日)
橘のケンカだんじりまつり:徳島県阿南市橘町海正八幡神社
日程:2024年10月1日(月)~10月3日(水)
堺(鳳)だんじり祭り:大阪府堺市大鳥神社ほか
日程:2024年9月28日(土)~10月1日(月)
だんじり祭り:大阪府貝塚市麻生郷地区ほか阿理莫神社ほか
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
大津地区だんじり祭:大阪府泉大津市大津地区大津神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
曽根・助松地区だんじり祭:大阪府泉大津市助松 曽根地区助松神社、曽根神社
日程:2024年10月5日(土)~10月48日(日)
泉穴師だんじり祭(飯の山だんじり):大阪府泉大津市豊中泉穴師神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
三日市だんじり祭:大阪府河内長野市喜多町・三日市町烏帽子形神社、赤坂上の宮神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
千代田地区だんじり祭:大阪府河内長野市市町千代田神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
聖神社だんじりまつり:大阪府和泉市聖神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
だんじり祭り:大阪府大阪狭山市狭山神社、池の原神社、三都神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
下山田八幡神社のだんじり祭:岡山県瀬戸内市邑久町下山田八幡神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
城崎だんじり祭り:兵庫県豊岡市城崎町湯島四所神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
十市町だんじり祭り:奈良県橿原市十市町十一御県座神社
日程:2024年10月5日(土)~10月6日(日)
いかがですか?たくさんの場所でだんじり祭りが行われていますよね!
多くのだんじり祭りが、岸和田と同様に敬老の日前の土日、若しくは、10月体育の日に絡む3連休で開催されます。
だんじりの意味
各地のだんじり祭りをご紹介しましたが、何かお気付きになったことはありませんか。
そうなんです。だんじり祭は西日本でのみ開催されているのです。
これには理由があります。
そもそも『だんじり』とは、お祭りの時に奉納される「山車(だし)」のことで、「だんじり」は西日本特有の呼び方なんです。

だんじりの由来には諸説あります。
一つは、屋台を動かすしたときに「じりじり」という摩擦音が出ることから、「台じり」という言葉が転化したというものです。
二つには、「山車(だし)」という言葉が方言に変わっていったという説です。
「だんじり」は、「壇尻」や「楽車」「台尻」「地車」「花車」「屋台」など実に多くの漢字表記があります。
このように多くの表現があるので、漢字自体に意味を求めるのは、あまり意味がないと言えるでしょう!
次に、だんじり祭りの発祥地についてですが、これも諸説あります。
江戸時代の元禄元年、堺市の開口神社の氏子が作った「鉾」が、だんじりの原型ではないかと言われています。華やかなりし時には、数十台のだんじりがあったことも記録されています。
一方、江戸時代から、秋の収穫の後の庶民の楽しみに一つとして、「屋台」とともに人々が練り歩いた事例が記録されています。
そしてこの行事は、京都の祇園祭の「山鉾巡業」の模倣だと言われています。
ただ、当時の屋台は、今日のように立派な彫り物がされていたわけではなく、いたってシンプルな形であったようです。
今のようなだんじりの原型が登場したのは、江戸の末期から明治にかけてではないかと言われています。
だんじり(山車)と神輿の違い
それでは、「だんじり」とよく似たもので、お祭りにも登場する「神輿(きこし)」との違いは何なのでしょうか?
小さいころから関東地方に住んでいる人にとっては、「だんじり」という言葉自体を知らない可能性が高いですから、なじみがあるのは、むしろ「神輿」の方でしょう。

私もよくよく記憶をたどっても、「山車」を見た覚えはありません。
さて、そこで「だんじり」と「神輿」の違いですが、この二つには大きな違いがあります。
まず、「だんじり」は、祭りの間だけ天から神様に降臨していただく場所、という設定です。
一方、「神輿」ですが、よく見ると形がすでに神社のようになっていますよね。つまり、既にそこに神様がいらっしゃる状態のものが「神輿」です。
お祭りの時に、神様が出かけられる際の乗り物という説もあります。
この違いもあり…
神様が乗る神聖なものとして人の手で高く掲げ(担ぎ)る、お神輿。
神様に楽しんでいただく意味も込め、人が乗り、お囃子で盛り上げる、だんじり。
という事なんですね。
いかがでしたか。
各地のだんじり祭りの情報や、だんじりの由来などについてご紹介してきました。
お伝えした情報も頭に置いて、今年の秋は、どこかのお祭りを覗いてみませんか?
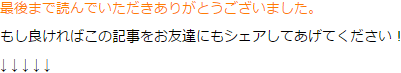
コメント
-
2014年 10月 04日トラックバック:ローカルニュースの旅
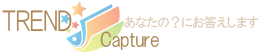
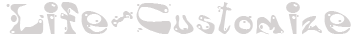
この記事へのコメントはありません。